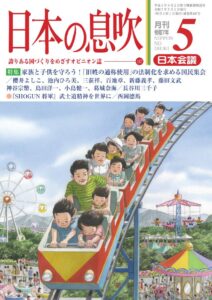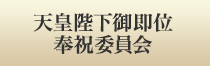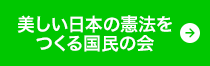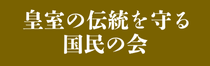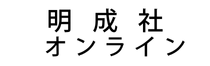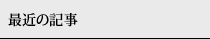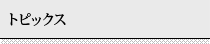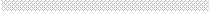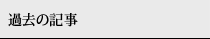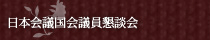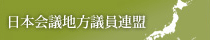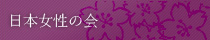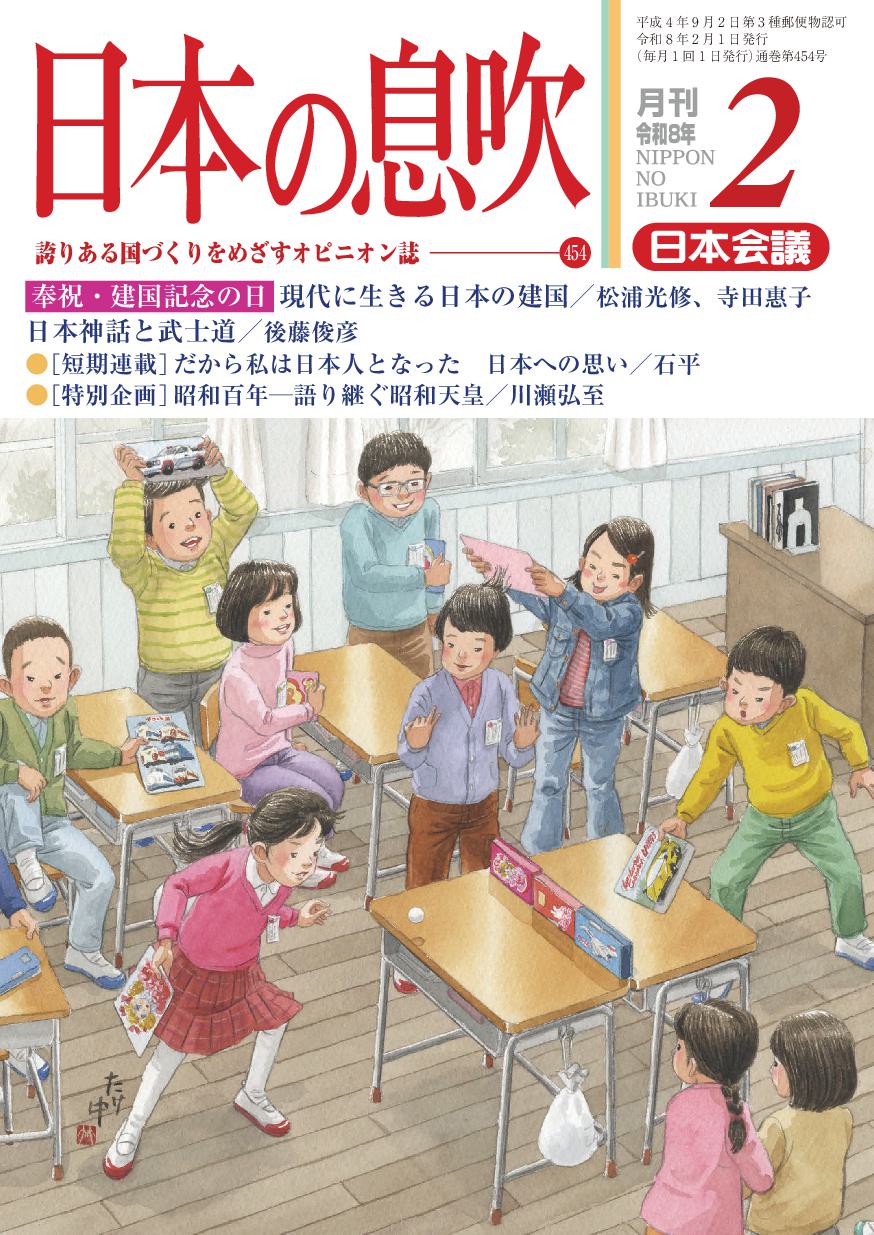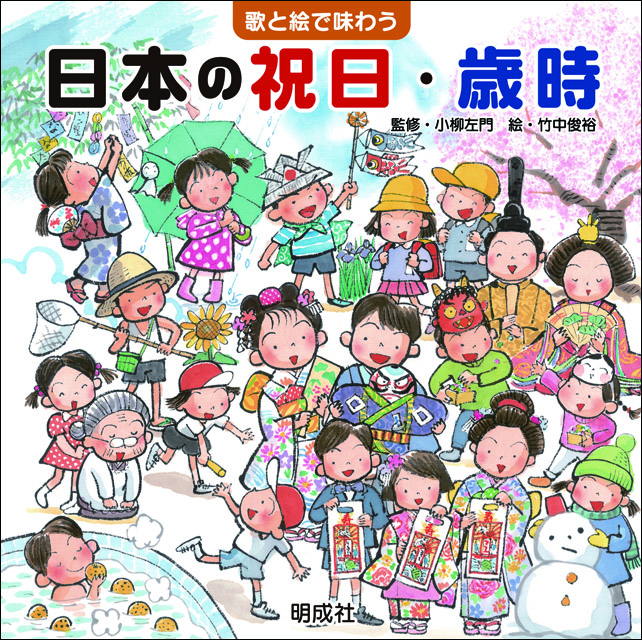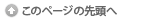【夫婦別姓問題】「システム設計」の問題として考える「夫婦別姓」(埼玉大学名誉教授・長谷川三千子氏)
議論が活発化している「選択的夫婦別姓」問題。
「名字が変わるのが嫌な人も、そうでない人も、それぞれの選択肢があれば良いのでは?」
一見もっともらしいこの意見に、私たちは立ち止まって考える必要があります。
『日本の息吹』5月号では、埼玉大学名誉教授の長谷川三千子先生が、この問題を単なる個人の選択の問題としてではなく、「システム設計」という視点から深く掘り下げています。
「姓」と「氏」の違いを理解する
長谷川先生は、議論の出発点として、「姓」と「氏」という二つの言葉が持つ意味の違いを明確にすることの重要性を指摘します。
- 姓:生まれた家、血筋を示すもの。
- 氏:夫婦が同じ家となり、共に歩む家族の証。
韓国の夫婦別姓制度のように「姓」のみで成り立つシステムでは、個人のルーツは明確になる一方で、夫婦という新しい家族の絆は表現されません。
一方、日本の民法は、明治時代に「氏」という概念を導入しました。これは、夫婦が同じ「氏」を称することで、社会の構成単位である「家族」としてのまとまりを示す、日本独自のシステムです。長谷川先生は、「氏」の導入は、「東アジアにおける家族システムの新機軸だつた」と述べています。
法務省のホームページでは、この重要な歴史的背景や東アジアの家族制度との違いに触れず、単に「姓」や「名字」を「氏」と呼んでいると説明するに留まっていますが、長谷川先生はこれを「ほとんど説明放棄だ」と厳しく指摘します。
自然でシンプルな「夫婦同氏」という形
最高裁判所の判決でも、「夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称することにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」と示されている通り、「夫婦同氏」は、家族という一つのまとまりを明確にする上で重要な役割を果たしています。
私たちの誰もが、どこかの家で生まれ育ち、その縦の繋がり(姓)なしに存在することはできません。しかし、人は成長し、新たな家庭を築きます。もとは他人だった二人が出会い、共に生きる決意を示す印、それが「同氏」なのです。そして、その家庭から、また新たな縦の絆が紡がれていきます。
このように考えると、日本の「夫婦同氏」制度は、人間のライフサイクルに寄り添った、実に自然でシンプルなシステムであることが理解できます。
「選択的夫婦別姓」という言葉の矛盾
もし、この「夫婦同氏」制度を崩し、「選択的夫婦別氏制度」へと変更したらどうなるでしょうか?
長谷川先生は、そもそも「夫婦別氏」という言葉自体が矛盾していると指摘します。「氏」は、血縁のない者同士が家族としての絆を共有するために生まれた概念だからです。「夫婦別氏」は、結婚と同時に離婚するような論理的な破綻を孕んでいます。
そのため、別氏論者たちは「夫婦別姓」という言葉を使いますが、本来の夫婦別姓制度は、個人の選択の余地はなく、出生時の姓を生涯変えないという厳格な出生第一主義に基づいた考え方です。
「選択的夫婦別姓」という言葉は、そうした背景を知らない人々に、あたかも簡単な選択肢が増えるだけのように誤解させているのです。
最も使いやすいシステムへ
「システム設計」という視点から見れば、日本の「夫婦同氏」制度の基本を堅持したまま、通称使用の法制化をしっかりと行うことこそが、最も使いやすい最良のシステム実現となるのではないでしょうか。
日本の大切な伝統と家族の絆を守りながら、より良い社会のあり方を考えていく。そのために、私たちはもっと深くこの問題について知る必要があると思います。
日本会議では、会員の皆様に、本稿のような日本の根幹に関わる問題について専門家の意見や深い分析を掲載した機関誌『日本の息吹』を毎月お届けしています。
日本について真剣に考える皆様にとって、きっと貴重な情報源となるはずです。
日本会議についてもっと知りたいという方は、
ぜひご入会、または無料のメールマガジンにご登録ください。