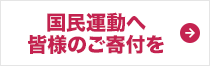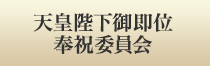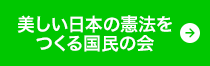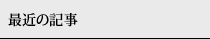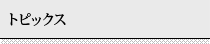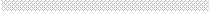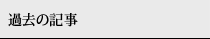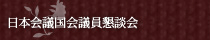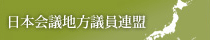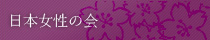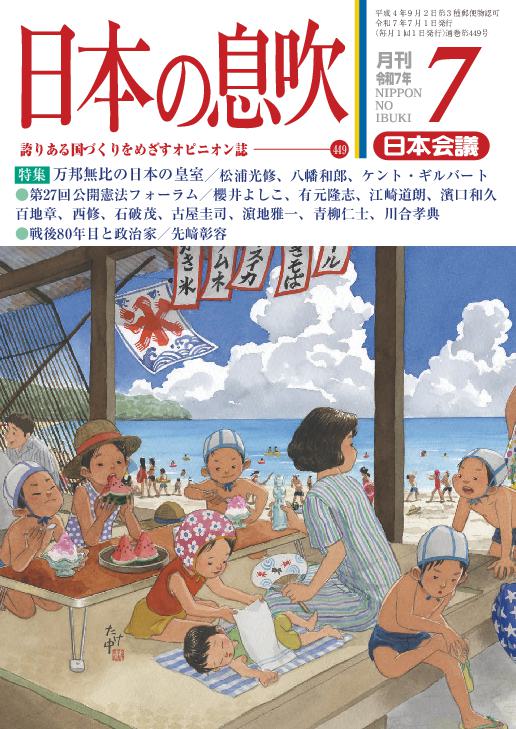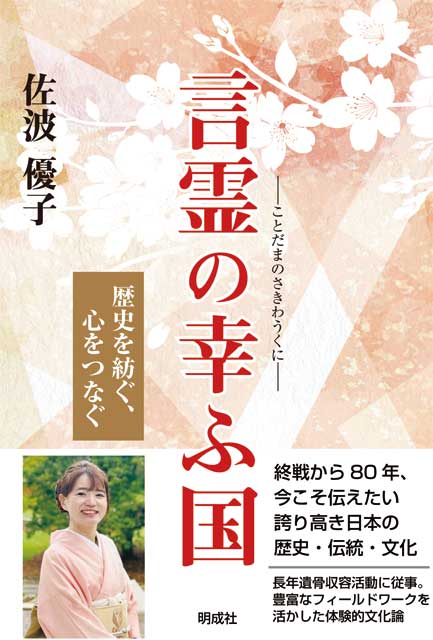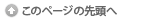平成29年5月の記事一覧
安倍首相「9条に自衛隊明記」「子どもたちこそ、我が国の未来」(メッセージ全文)(平成29年5月8日)
憲法記念日の3日、全国各地で憲法改正を訴える集会が開かれました。
東京・永田町で開催された「第19回公開憲法フォーラム」(共催:民間憲法臨調、美しい日本の憲法をつくる国民の会)には、自民党の古屋圭司衆議院議員、公明党の遠山清彦衆議院議員、日本維新の会の足立康史衆議院議員が登壇し、櫻井よしこ氏のコーディネートで今後の国会審議の進め方や改憲テーマについて、熱心な議論を行いました。また、この行事には安倍晋三自民党総裁がビデオメッセージを寄せ、憲法9条の改正や、公教育への国の責任について踏み込んだ発言を行うとともに、東京五輪が開催される2020年を目標として憲法改正を実現していきたいと抱負を述べました。
東京会場には「日本のこころ」の中山恭子参議院議員ら在京の国会議員をはじめ、従来よりも多い1150名の参加者を得るとともに、全国約40カ所に同時中継されました。
第19回公開憲法フォーラム(5月3日)
安倍晋三自由民主党総裁メッセージ全文
◇ ◇ ◇
ご来場の皆様、こんにちは。「自由民主党」総裁の安倍晋三です。
憲法施行70年の節目の年に、「第19回公開憲法フォーラム」が盛大に開催されましたことに、まずもって、お慶びを申し上げます。
憲法改正の早期実現に向けて、それぞれのお立場で、精力的に活動されている皆様に、心から敬意を表します。憲法改正は、自由民主党の立党以来の党是です。
自民党結党者の悲願であり、歴代の総裁が受け継いでまいりました。
私が総理・総裁であった10年前、施行60年の年に国民投票法が成立し、改正に向けての一歩を踏み出すことができましたが、憲法はたった一字も変わることなく、施行70年の節目を迎えるに至りました。
憲法を改正するか否かは、最終的には、国民投票によって、国民が決めるものですが、その発議は国会にしかできません。私たち国会議員は、その大きな責任をかみしめるべきであると思います。
次なる70年に向かって日本がどういう国を目指すのか。今を生きる私たちは、少子高齢化、人口減少、経済再生、安全保障環境の悪化など、我が国が直面する困難な課題に対し、真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。憲法は、国の未来、理想の姿を語るものです。
私たち国会議員は、この国の未来像について、憲法改正の発議案を国民に提示するための、「具体的な議論」を始めなければならない、その時期に来ていると思います。
我が党、自由民主党は、未来に、国民に責任を持つ政党として、憲法審査会における、「具体的な議論」をリードし、その歴史的使命を果たしてまいりたい、と思います。
例えば、憲法9条です。今日、災害救助を含め、命懸けで、24時間、365日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く、その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。
しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、今なお存在しています。
「自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば、命を張って守ってくれ」というのは、あまりにも無責任です。
私は、少なくとも、私たちの世代の内に、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである、と考えます。
もちろん、9条の平和主義の理念については、未来に向けて、しっかりと、堅持していかなければなりません。そこで、「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という考え方、これは、国民的な議論に値するのだろう、と思います。
教育の問題。
子どもたちこそ、我が国の未来であり、憲法において、国の未来の姿を議論する際、教育は極めて重要なテーマだと思います。
誰もが生きがいを持って、その能力を存分に発揮できる「一億総活躍社会」を実現する上で、教育が果たすべき役割は極めて大きい。
世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、経済状況にかかわらず、子どもたちが、それぞれの夢に向かって頑張ることができる、そうした日本でありたいと思っています。
70年前、現行憲法の下で制度化された、小中学校9年間の義務教育制度、普通教育の無償化は、まさに、戦後の発展の大きな原動力となりました。
70年の時を経て、社会も経済も大きく変化した現在、子どもたちがそれぞれの夢を追いかけるためには、高等教育についても、全ての国民に真に開かれたものとしなければならないと思います。
これは、個人の問題にとどまりません。人材を育てることは、社会、経済の発展に、確実につながっていくものであります。これらの議論の他にも、この国の未来を見据えて議論していくべき課題は多々あるでしょう。
私は、かねがね、半世紀ぶりに、夏季のオリンピック、パラリンピックが開催される2020年を、未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだと申し上げてきました。
かつて、1964年の東京五輪を目指して、日本は、大きく生まれ変わりました。その際に得た自信が、その後、先進国へと急成長を遂げる原動力となりました2020年もまた、日本人共通の大きな目標となっています。
新しく生まれ変わった日本が、しっかりと動き出す年、2020年を、新しい憲法が施行される年にしたい、と強く願っています。
私は、こうした形で国の未来を切り拓いていきたいと考えています。本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。
これを契機に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命を、しっかりと果たしていく決意であることを改めて申し上げます。
最後になりましたが、国民的な議論と理解を深めていくためには、皆様方、「民間憲法臨調」、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」のこうした取組みが不可欠であり、大変心強く感じております。
憲法改正に向けて、ともに頑張りましょう。
5月3日各党は具体的な憲法改正原案の提案を!決議文全文(平成29年5月8日)
民間憲法臨調と美しい日本の憲法をつくる国民の会では、5月3日に開催した第19回
公開憲法フォーラムの中で「憲法改正原案を提示して国会における合意形成を図り、憲法
改正の国会発議および国民投票の実施」を求め声明文を採択しました。
この声明文は、両団体から、自民党、公明党、維新の3党に手交されました。
声明の全文は以下の通りです。
◇ ◇ ◇
憲法施行七十年、各党は具体的な憲法改正原案の提案を!
日本国憲法が施行から七十年を迎えるにいたった。この間、わが国ではただの一度も憲
法が改正されることはなかった。衆参両院でそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成がなけ
れば、憲法改正の是非を国民に問う発議すらできず、しかも国民投票を不可欠とする世界
でも類例のない厳しい条件が課せられているからである。
その意味で昨年七月の参議院選挙では、戦後史を画する重大な政治選択がなされた。衆
議院に引き続き、参議院でも憲法改正に前向きな諸政党が憲法改正の発議に必要な三分の
二以上の議席を占めるにいたった。
現在、わが国を取り巻く内外の情勢は大きく変貌している。北朝鮮による度重なる弾道
ミサイルの発射は、核開発とも相まって、わが国のみならず世界の安全保障にとって深刻
な脅威となりつつある。また軍事力を背景に東シナ海・南シナ海における海洋覇権の獲得
の動きを強めている中国については、昨年来、尖閣諸島の実効支配に向けた取り組みを実
行する段階に入った可能性があると指摘されている。その一方で、脅威にさらされている
わが国の平和と国民の命を守るべき自衛隊については、憲法ではその存在自体が規定され
ていない状態が放置されたままとなっている。それゆえすみやかに憲法九条に自衛隊を明
記すべきである。
またわが国は東日本大震災を経験し、今後も近い将来に首都直下地震や南海トラフ地震
の発生が予測されている。しかしながら現行憲法には、大規模自然災害その他の事態へ対
処するための緊急事態条項が存在していない。世界各国で常識となっている緊急事態条項
が現行憲法にないのは、憲法の根本的欠陥以外の何物でもない。
参議院選挙によってようやく本格的に憲法改正が検討される政治環境が整ったことを受
け、国民が憲法改正論議の具体的な進展を望んでいることが、各種世論調査において明確
に示されている。たとえば昨年十一月に実施された読売新聞世論調査では、六十七%が衆
参両院に設置された憲法審査会における憲法改正に向けた議論が活発に行われることを期
待するとし、また同じ時期のFNN世論調査では、八十一・四%が各政党はそれぞれの憲
法草案を提示すべきだとしている。
第十九回公開憲法フォーラムの開催にあたり、国民のこの期待に応え、国民の命と暮ら
しを守る国家の責任を果たすため、各党に対して、憲法改正原案を提示して国会における
合意形成を図り、憲法改正の国会発議および国民投票の実施をすみやかに実現するよう要
望する。
右、声明する。
平成二十九年五月三日
「二十一世紀の日本と憲法」有識者懇談会(通称 民間憲法臨調)
美しい日本の憲法をつくる国民の会